



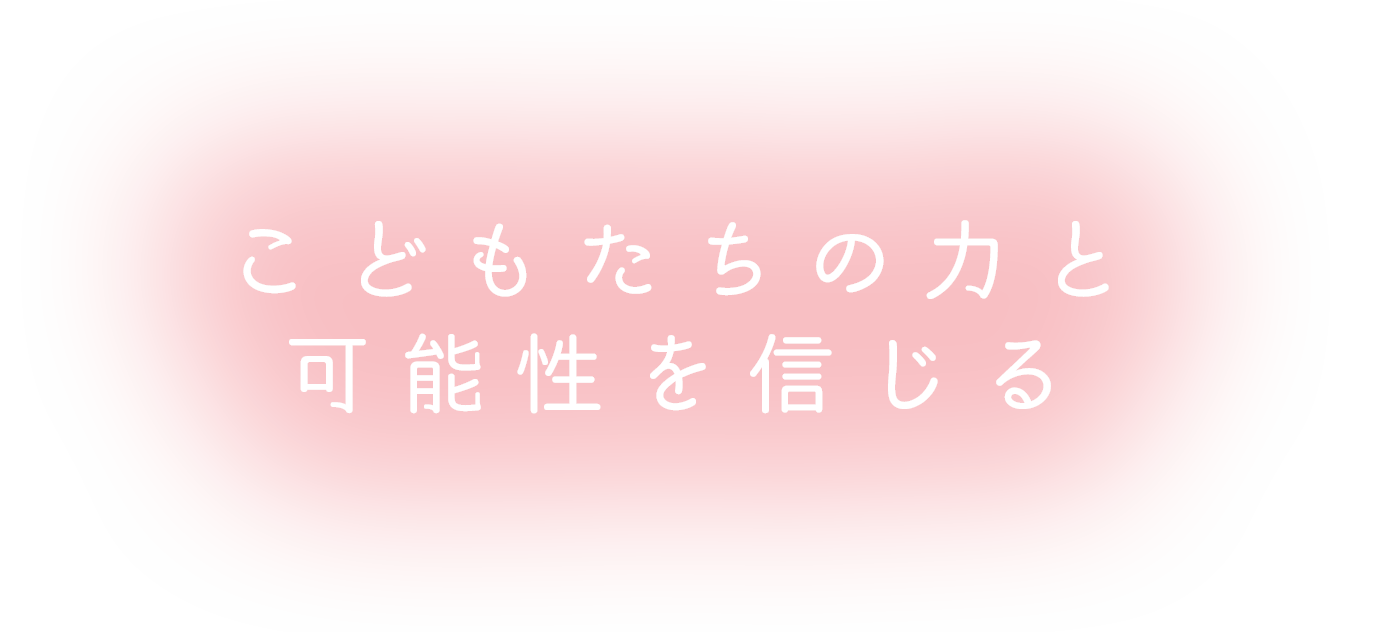
保育目標goal
みんなを思いやりながら、自分たちの未来をつくる力を育みたい
-
共感性
自分の気持ちを大切にし
他者の気持ちも大切にするこども
-
内発性
自らの内なる声を聴き
主体的に動くこども
-
創造性
自由に考え
創造するこども
入園をご希望の方へrequest
保育園の様子 Instagram
インスタグラムで
保育園の様子が見られます!




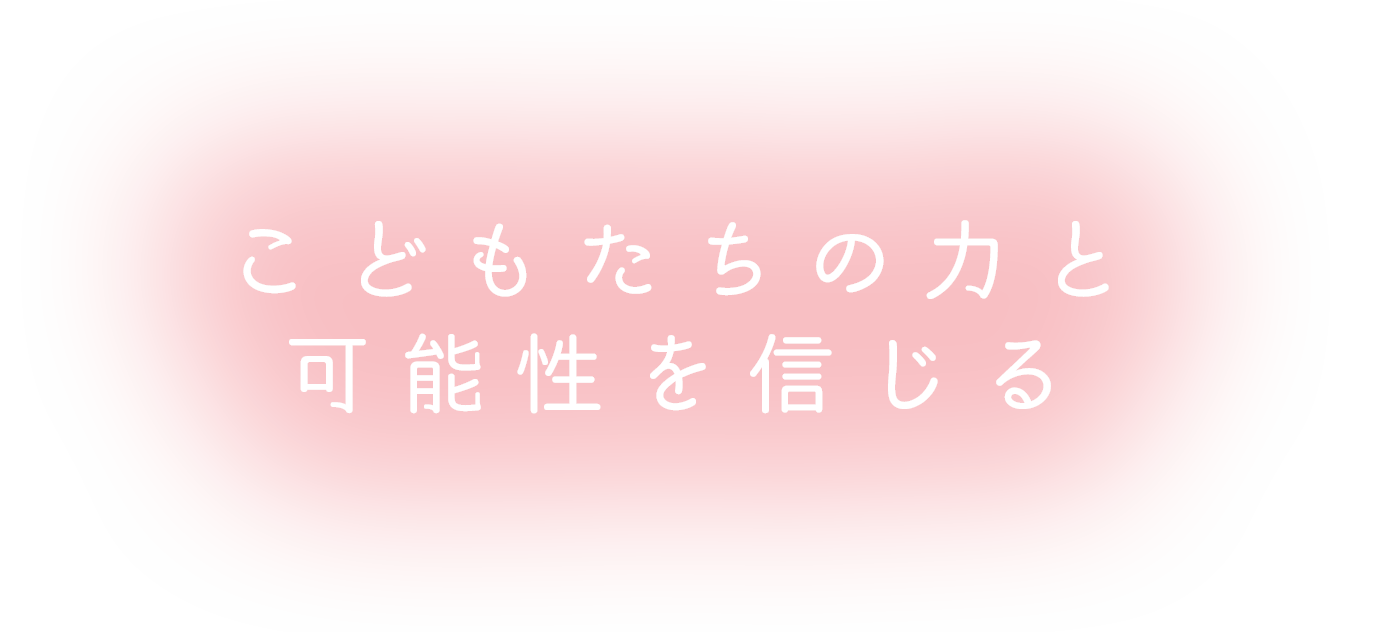
みんなを思いやりながら、自分たちの未来をつくる力を育みたい
自分の気持ちを大切にし
他者の気持ちも大切にするこども

自らの内なる声を聴き
主体的に動くこども

自由に考え
創造するこども

インスタグラムで
保育園の様子が見られます!